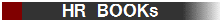 書評 2025.05 書評 2025.05
ジョブ型人事の道しるべ
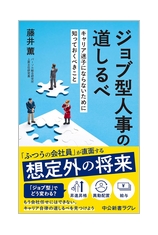 長年勤めてきたからという累積貢献度は薄れ,現時点での実力で評価されるジョブ型人事につき「ふつうの会社員」を基準にインパクトを考察していく1冊。随所に主要企業の人事担当者の生の声を紹介しながら,日本企業がジョブ型にシフトしていく目的を,①人件費管理の合理性,②タレントマネジメントの2点に分けて解き明かしていく。ただ,日本では職種別賃金は浸透せず,依然「どの企業に属しているか」が賃金格差を決定づける実態だとも見抜き,“日本型”ともいうべき幅のある特徴を見出している。指摘されてみれば,無期雇用・正社員・総合職の場合,教科書通りのジョブ型にはならないと合点がいく。一方で,同じ仕事を続ける限り給料は上がらない仕組みであり,管理職の場合は任期を設け「よりベターな人材に置き換えていく」と公言する会社もあることから,「給料の高いおじさん・おばさんはいなくなっていく」と予想。天才でも業界第一人者でもないふつうの会社員が目指す道は何かと問い,キャリアのヒントをガイドしている。
長年勤めてきたからという累積貢献度は薄れ,現時点での実力で評価されるジョブ型人事につき「ふつうの会社員」を基準にインパクトを考察していく1冊。随所に主要企業の人事担当者の生の声を紹介しながら,日本企業がジョブ型にシフトしていく目的を,①人件費管理の合理性,②タレントマネジメントの2点に分けて解き明かしていく。ただ,日本では職種別賃金は浸透せず,依然「どの企業に属しているか」が賃金格差を決定づける実態だとも見抜き,“日本型”ともいうべき幅のある特徴を見出している。指摘されてみれば,無期雇用・正社員・総合職の場合,教科書通りのジョブ型にはならないと合点がいく。一方で,同じ仕事を続ける限り給料は上がらない仕組みであり,管理職の場合は任期を設け「よりベターな人材に置き換えていく」と公言する会社もあることから,「給料の高いおじさん・おばさんはいなくなっていく」と予想。天才でも業界第一人者でもないふつうの会社員が目指す道は何かと問い,キャリアのヒントをガイドしている。
●著者:藤井 薫 ●発行:中央公論新社
●発行日:2025年2月10日 ●体裁:新書版/255頁
静かに分断する職場
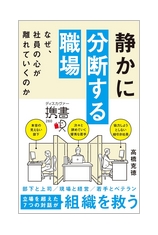 個々人が目の前の仕事を一生懸命にやっているだけの状態は「閉じこもる働き方」だと著者は危惧し,同僚が助け合える仲間ではなく,人との関係が希薄化している組織の問題点を指摘する。「仕事が面白い,職場が楽しい,会社が好きだ」という活力はバブル崩壊以降に失われたと振り返り,その原因は目の前の生産性にこだわるあまり設備投資と配当を逆転させてしまった構造改革にあったのではないかと疑いを強くする。さらにコロナ禍では物理的な分断も起き,見えない壁がエンゲージメントを下げていると憂う。本質的な対話がなく,互いに距離を置いている状態を「静かな分断」と定義し,それを乗り越える組織開発のアプローチを「5つのカギ」に整理。また,静かな分断を超えるためのテーマを7つ(仕事,働き方,職場,管理職,リーダーシップ,未来,会社)列挙し,メンバーと対話し,探求するワークを紹介している。コミュニティの力を取り戻そうとする強い決意と,違いがあっても対話をあきらめない粘り強さがにじむ“熱い”内容だ。
個々人が目の前の仕事を一生懸命にやっているだけの状態は「閉じこもる働き方」だと著者は危惧し,同僚が助け合える仲間ではなく,人との関係が希薄化している組織の問題点を指摘する。「仕事が面白い,職場が楽しい,会社が好きだ」という活力はバブル崩壊以降に失われたと振り返り,その原因は目の前の生産性にこだわるあまり設備投資と配当を逆転させてしまった構造改革にあったのではないかと疑いを強くする。さらにコロナ禍では物理的な分断も起き,見えない壁がエンゲージメントを下げていると憂う。本質的な対話がなく,互いに距離を置いている状態を「静かな分断」と定義し,それを乗り越える組織開発のアプローチを「5つのカギ」に整理。また,静かな分断を超えるためのテーマを7つ(仕事,働き方,職場,管理職,リーダーシップ,未来,会社)列挙し,メンバーと対話し,探求するワークを紹介している。コミュニティの力を取り戻そうとする強い決意と,違いがあっても対話をあきらめない粘り強さがにじむ“熱い”内容だ。
●著者:高橋克徳 ●ディスカヴァー・トゥエンティワン
●発行日:2025年3月22日 ●体裁:新書版/303頁
離職率が下がる!生産性が上がる!!「すごい面談」
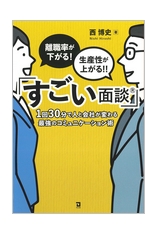 自律・自立型社員を育てる人材育成コンサルティングを手がけている著者は,独自の面談技法を体系化し『すごい面談』と名付け,『面談士』という資格を創設。本書では,受講生(A社長・B社長)とともにその講義とワークを再現している。社員面談は3ヵ月に1回,各回30分でいいという。また,この面談技法は「営業成績が不振なとき」「コンプライアンス違反が疑われるとき」「ミスが頻発するとき」「四半期・半期での評価面接」等でも応用できるとメリットを挙げている。ステップは6段階(①事前準備,②事実確認・原因のヒアリング,③期待値の伝達・理想像のすり合わせ,④方法論の検討,⑤助言の提供,⑥計画の策定),これに3つの「やってはいけないこと」が加わる。「面談準備シート」「面談評価シート」を公開し,模擬面談事例を活字で再現。ポイントは指示命令ではなく,ゴールを明確にしたうえで,アドバイスを伝えるコーチングの要素にある。社員と信頼関係を築き,可能性を引き出すマネジメントのヒントが学習できそうだ。
自律・自立型社員を育てる人材育成コンサルティングを手がけている著者は,独自の面談技法を体系化し『すごい面談』と名付け,『面談士』という資格を創設。本書では,受講生(A社長・B社長)とともにその講義とワークを再現している。社員面談は3ヵ月に1回,各回30分でいいという。また,この面談技法は「営業成績が不振なとき」「コンプライアンス違反が疑われるとき」「ミスが頻発するとき」「四半期・半期での評価面接」等でも応用できるとメリットを挙げている。ステップは6段階(①事前準備,②事実確認・原因のヒアリング,③期待値の伝達・理想像のすり合わせ,④方法論の検討,⑤助言の提供,⑥計画の策定),これに3つの「やってはいけないこと」が加わる。「面談準備シート」「面談評価シート」を公開し,模擬面談事例を活字で再現。ポイントは指示命令ではなく,ゴールを明確にしたうえで,アドバイスを伝えるコーチングの要素にある。社員と信頼関係を築き,可能性を引き出すマネジメントのヒントが学習できそうだ。
●著者:西 博史 ●発行:同友館
●発行日:2025年3月30日 ●体裁:四六版/272頁
組織と働き方の本質
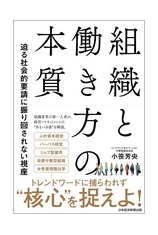 モチベーションエンジニアリングの第一人者である著者は,今の日本で注目されているマネジメントのバズワードを懐疑的に見て,改めて本質に届いているかを問い直す。「個人と組織」では,Aが悪いかBが悪いかではなく,AとBの「間」に問題があると物事を見抜く着眼点を諭す。社会的要請の課題からは「女性管理職比率」「人的資本経営」「働き方改革」「ジョブ型雇用」の4テーマを取り上げ,数値目標ありきの「短絡的なやり方には呆れる」と危機感を募らせる。同様に組織変革の課題では「ダイバーシティ」を例に,事業戦略とかみ合わずに多様性ありきのマネジメントに走る滑稽さを指摘し,経営と多様性の関係は「目的と手段」ではなく「原因と結果」にすぎないと看破する。個人の働き方では,小さな枠で「ワークライフバランス」を固めるのではなく,あえて均衡を崩し,バランスの幅を大きくとって成長を目指せとアドバイス。組織・個人ともに均衡に安住し,手段と目的を取り違える病から抜け出すよう,気づきを促す視座を提供してくれる。
モチベーションエンジニアリングの第一人者である著者は,今の日本で注目されているマネジメントのバズワードを懐疑的に見て,改めて本質に届いているかを問い直す。「個人と組織」では,Aが悪いかBが悪いかではなく,AとBの「間」に問題があると物事を見抜く着眼点を諭す。社会的要請の課題からは「女性管理職比率」「人的資本経営」「働き方改革」「ジョブ型雇用」の4テーマを取り上げ,数値目標ありきの「短絡的なやり方には呆れる」と危機感を募らせる。同様に組織変革の課題では「ダイバーシティ」を例に,事業戦略とかみ合わずに多様性ありきのマネジメントに走る滑稽さを指摘し,経営と多様性の関係は「目的と手段」ではなく「原因と結果」にすぎないと看破する。個人の働き方では,小さな枠で「ワークライフバランス」を固めるのではなく,あえて均衡を崩し,バランスの幅を大きくとって成長を目指せとアドバイス。組織・個人ともに均衡に安住し,手段と目的を取り違える病から抜け出すよう,気づきを促す視座を提供してくれる。
●著者:小笹芳央 ●発行:日経BP/日本経済新聞出版
●発行日:2025年4月9日 ●体裁:四六版/224頁
HRM Magazine.
|

