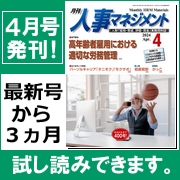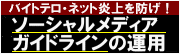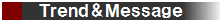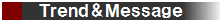
「研修やりっ放し」からの脱却
ビジネスコーチ(株) 取締役副社長 橋場 剛
■一律的な集合研修の限界
ビジネスの現場では,以下のような質問が投げかけられることがあります。
・自社における集合研修は,どの程度ビジネスの現場で効果的に活かされていますか?
・集合研修に注ぎ込んできた膨大な費用と時間は,どの程度のビジネスリターン(成果)を生み出していますか?
残念ながら,これらの問いに対して明確に答えられる企業は多くなく,一律的な集合研修の限界に気づき始めた企業は人材育成投資のアプローチを「集合型(1対N)」から「個別(1対1)」へと転換しつつあります。より正確にいえば,「集合研修のやりっ放し」で終わらせないために,その後のフォローアップとして「個別(1対1)コーチング」を採用する企業が着実に増えつつあります。
「月曜日の朝問題」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。受講者が,研修時間中には気づきや学びを得て一時的に仕事に対するモチベーションを上げたとしても,土日を過ごし月曜日の朝を迎えると,先週学んだことはすっかり抜け落ち,研修内容がビジネスの現場で活かされない現象を揶揄したものです。最近では,動画コンテンツやYouTubeの充実などもあり,一般的な知識のインプットだけが目的の場合は,わざわざ同じ空間に多くの人を集めて研修を行う意味自体が消滅しつつあります。
一律的な集合研修の限界を解決する効果的なアプローチとして選ばれているのが,「個別(1対1)コーチング」によるフォローアップです。「研修やりっ放し」はダイエットに置き換えると,「糖質控えめな食事」と「適度な運動」にせっかく取り組んだにもかかわらず,「体重計に定期的に乗っていない」のと同じです。いわゆる「リバウンド」をさせないよう「体重計に乗る」というフォローアップを「定期的に」行うことが不可欠です。
■個別(1対1)コーチングの意義と3つの問い
「研修やりっ放し」で終わらないための個別(1対1)コーチングの意義は次の3点です。
①一人ひとりに合った効果的なフォローアップを行うことができること
②「やらされ感」(受け身)を「自分ごと」(主体性)に転換できること
③「一過性」の取り組みではなく,「習慣化」「定着化」までを支援できること
具体的には,研修後に実施するフォローアップのコーチングで以下の3つを問いかけます。
【問いかけ1】研修で学んだことの中で,最も重要なことは何でしたか?
【問いかけ2】それを自身の仕事でどのように活用すると最も効果的ですか?
【問いかけ3】自身の仕事での活用をいつから始めますか?(いつまでにやりますか?)
こうした問いを契機に自分の言葉で「実行プラン」を語ることによって,やらされ感はなくなり,自ら選んだ「自己決定の行動」であるがゆえに実践へのコミットメントが高まります。
また,自らに対して「フォローアップの問い」を立てることも有効です(セルフコーチング)。例えば「連休中に得た経験や学びを,連休明けの仕事にどのように活かすか?」という問いを自ら立ててみるのです。自ら投げかけた(または第三者から投げかけられた)問いが,自身の前向きな行動を生み出し,「バタフライエフェクト」として周囲に対してポジティブなインパクト(影響力)を生み出し巡り巡ってハリケーン(組織活性化)を作り出すことにもつながるかもしれません。
(月刊 人事マネジメント 2025年5月号 HR Short Message より)
HRM Magazine.
|